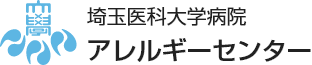2025年10月16日夕方、第79回アレルギーフォーラムが現地とWebのハイブリッド形式にて開催されました。
近年、消化管アレルギーへの対応の重要性が高まっていますが、病態が多様であることから、診断や治療に難渋することも少なくありません。今回は、東海大学医学部小児科教授の山田佳之先生をお迎えし、「消化管のアレルギー疾患―最近の話題―」というタイトルで、埼玉医科大学第3講堂にてご講演をいただきました。
山田先生は、食物アレルギーを「即時型」「好酸球性消化管疾患(eosinophilic gastrointestinal disorders:EGIDs)」「Non-IgE型食物アレルギー(non-IgE-mediated gastrointestinal food allergies:non-IgE-GIFAs)」に分類し、それぞれの病態や診療上の要点について、最新の知見を交えてご解説くださいました。
まず、EGIDsは好酸球の消化管への高度な浸潤により消化器症状をきたすアレルギー性炎症性疾患であり、EoE(好酸球性食道炎)など病変部位によって分類されます。診断には内視鏡検査および生検による組織学的評価が必須です。治療はPPI、ステロイドなどであり、原因となる食物アレルゲンが特定できた場合は原因食物の除去が基本です。再燃例や難治例では生物学的製剤が有用な場合もあるそうです。
一方、新生児・乳児食物蛋白誘発胃腸症は、主に牛乳を原因として嘔吐・血便・下痢などを呈する非IgE依存性疾患です。従来「新生児・乳児消化管アレルギー」として扱われてきた疾患群を国際的概念に基づき再定義したもので、FPIES(Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome)、FPIAP(food protein-induced allergic proctocolitis)、FPE(food protein-induced enteropathy)が含まれます。近年では卵黄や大豆、コメ、小麦などによる固形食(solid)FPIESの増加や成人例の報告もあり、病態の多様化が指摘されています。FPIESの急性期には救急対応が必要であり、アドレナリンの効果は乏しく、十分な輸液管理が重要とされています。診断は除去・負荷試験が基本で、治療は原因食物の除去が中心となります。さらに、山田先生は、今年度より「卵黄食物蛋白誘発胃腸炎(FPIES)重症化予防のための管理方法の確立」をテーマとしたAMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)の研究を開始されたことをご紹介されました。本研究では、発症メカニズムの解明や診断・治療の指標となるバイオマーカーの特定を目指しており、今後の診療の発展に大きく寄与することが期待されます。
本フォーラムを通じて、消化管アレルギー疾患に対する理解が一層深まり、日常診療の質の向上に資する有意義な機会となりました。山田先生には、貴重なご講演を賜りましたこと、この場をお借りして心より御礼申し上げます。
(文責:小児科 板澤寿子)
 ご講演いただいた山田佳之先生
ご講演いただいた山田佳之先生