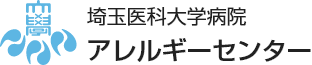第65回日本呼吸器学会学術講演会が、東京国際フォーラムで開催されました。隔年で東京国際フォーラムにて開催されています。今回は鹿児島大学呼吸器内科の井上博雅先生が会長でした。呼吸器内科は「守備範囲が広い学問」と思いますが、米国胸部疾患学会(ATS)のannual meetingを思わせるような、今回も多様な呼吸器疾患に対応したプログラムとなっており、参加するだけでとても刺激になります。また呼吸器内科医のリクルートにも力を入れていて、医学生・初期研修医を対象にした「呼吸器病学ことはじめ」も開催されています。

会長の井上博雅先生(鹿児島大学呼吸器内科)
日本アレルギー学会との共同企画「喘息予防管理ガイドライン(JGL)2024をふまえて」が開催され、永田センター長が座長、私は「JGL2024の治療ステップ~オプション治療を含めて」の講演を担当しました。喘息予防・管理ガイドライン(JGL)2024においては、策定委員会(喘息予防・管理ガイドライン2024WG)のメンバーにいれていただきましたが、JGL2024における喘息長期管理の概要について、我々のアレルゲン免疫療法のデータもふまえ、講演しました。日曜日の朝早いセッションにもかかわらず、多くの参加がありました。

座長の永田先生と講演する筆者
ポスター発表では、堀内先生が「急性好酸球性肺炎の気管支肺胞洗浄液におけるアンフィレギュリン濃度の解析」、石井先生が「非重症・重症喘息におけるFeNOと血中好酸球数に基づいたエンドタイプ別の臨床的寛解達成率」、当科OBで現在山梨医大の星野先生が「喘息患者における血清中IL-36 subfamilyと炎症性サイトカインの解析」について、発表くださいました。注目される分野の研究発表で、興味深かったと思います。杣教授はミニシンポジウム「臨床的寛解と表現型」の座長を担当されました。
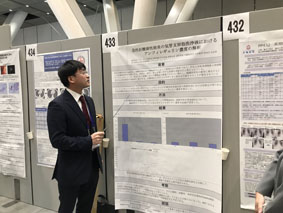
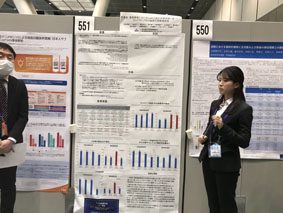
発表する堀内先生と石井先生
今回は、5年生のときに呼吸器内科に実習に来てくれた現在6年生の学生さんが参加してくれて、「呼吸器病学ことはじめ」にも参加してくれました。国際フォーラムは初めてとのことでしたが、学会の雰囲気を楽しんでくれたと思います。病院実習の間に愛知から来てくれるなど、彼らのやる気にも刺激され、我々もますます頑張っていかないといけないと思いました。

6年生と星野先生と筆者
(文責:呼吸器内科 中込一之)